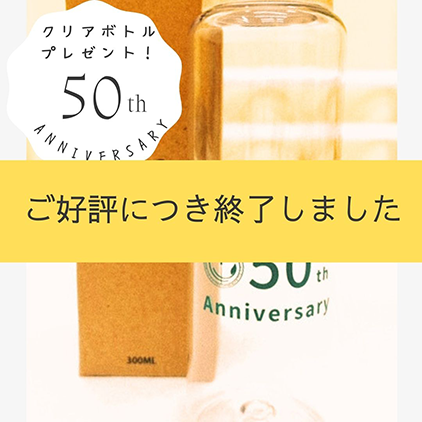月刊 堂島だより
早いもので9月となりました。
「9月病」という言葉があります。体調を崩しやすいこの季節。主な原因は、寒暖差によるストレス、睡眠不足、栄養の偏りなどがあげられます。
- なんとなく体がだるい
- 疲れがとれにくい
- やる気がでない
- 便秘や下痢になる
- 頭痛や肩こり
- 食欲不振や消化不良
そんな自律神経の乱れや、あらゆる不調を感じた際、おすすめのセルフケアが「お灸」です。
お灸とは
「鍼灸治療」の一種です。
もぐさを燃やした熱で経穴(ツボ)を刺激しさまざまな症状を緩和する東洋医学の治療です。薬を使わず、自然治癒力を高めます。
その方法は
- もぐさを直接皮膚上で燃焼させる
- 台などを挟んで間接的に温める(輻射熱)
この2つに分けられます。
お灸の種類
直接灸(ちょくせつきゅう)
「鍼灸治療」の一種です。
もぐさを燃やした熱で経穴(ツボ)を刺激しさまざまな症状を緩和する東洋医学の治療です。薬を使わず、自然治癒力を高めます。
皮膚の上に直接もぐさを置き温める方法
[効果]
- イボやタコなどの治療
※当院では行っていません
間接灸(かんせつきゅう)
もぐさと皮膚の間に台などを挟んで間接的に温める方法
[効果]
- 冷えや生理痛
- 筋肉疲労
- 自律神経の乱れなど
※当院が行っている方法
お灸の効果
皮膚の上で直接もぐさを燃焼させる方法は豊臣秀吉をはじめとする戦国武将たちが日頃から健康のために行っていました。
かの俳聖である松尾芭蕉も「三里に灸すゆるより松島の月まづ心にかかりて」という一節を「奥の細道」の序文に添えています。足のすねにある三里のツボにお灸をし、足の疲れを癒やしていたことがうかがえます。
このように、歴史上の人物も行っていた
[お灸でセルフケア]
その方法は
- 肩こり頭痛、腰痛、足の疲れ
- 冷え性、生理痛、月経前症候群
- 情緒不安定・気分の落ち込み
- 筋肉痛・神経痛
- 胃腸の不調
など、自分の体調に関連する経穴(ツボ)にお灸をすることで、熱による刺激で症状が緩和されます。皆様もぜひ[お灸セルフケア]を取り入れてみてください。
※慢性的な症状の場合、すぐに効果は得にくいですが継続することで変化があらわれてきます。
自分でお灸をする際の注意点
- 入浴直後は刺激を強く感じる可能性があります
- 妊娠中は医師にご相談ください
- 熱さやかゆみを我慢せず、すぐにお灸を外してください
- 火を使う際は燃えるものなど身の回りに置かないでください
堂島コラム
無病息災を願い、お灸をすえる〝二日灸(ふつかきゅう)〟
旧暦の2月2日と8月2日は[二日灸(ふつかきゅう)]といわれ、いつもの何倍もの効果が期待でき、無病息災で暮らせるというものです。
昔は春の農事と秋の収穫を前に体調を整えておく必要があり、こういった習わしが存在するとのこと。
旧暦8月2日、2024年では9月4日となります。皆さまも不調を感じる箇所に無病息災を願い、お灸をすえてみてはいかがでしょうか(^^)

火を使わずにできるお灸を販売しております。
お気軽にお声かけください。