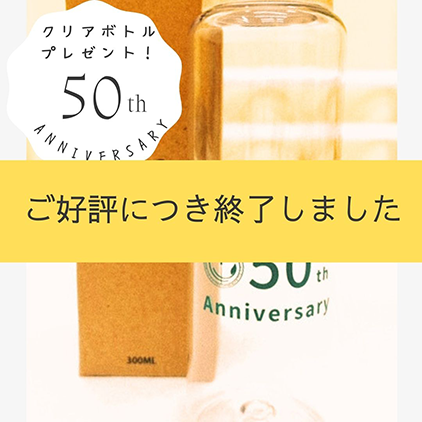スタッフブログ
実は平安時代から存在している。
カテゴリ:スタッフからお知らせ
堂島針灸接骨院 受付阪口です🍢
朝晩が冷え込むようになり、鍋料理がよりおいしくなる時期ですね🙏
先日、家族がおでん🍢を作ってくれていたので食べていたのですが。。

(↑うちは昆布出汁で煮込んでカラシで食べる派です🙏)
そういえば、おでんっていつから存在するんだろう?🤔
と、思い、少し調べてみました😂
🍢おでんの歴史まとめ🍢
⚫︎平安時代
豆腐を四角く切って竹串を刺して焼いて塩をかけて貴族が食べていた豆腐田楽
⚫︎室町時代
豆腐田楽に味噌をつけて食べるようになる
さらに、「お」をつけて「おでん」と略称で呼ばれる
⚫︎江戸時代
豆腐以外(こんにゃくやナスなど)の田楽が増える
庶民の間でスナック菓子感覚でおでん大流行
しかし、焼き上がるのを待っていられない江戸っ子たちは、焼くことをやめ、醤油で味付けた汁で煮込むことに
(一方関西地方では、昆布出汁で煮込んでから味噌をつけて食べるという食べ方が流行っていた)
⚫︎明治時代
練り物が誕生し、おでんの具材が増え、関東の煮込みおでんも徐々に関西に広まり、それぞれの地域でアレンジが加えられ、現代へ
簡単で美味しくてすぐ食べれるレシピに変化しているのが、今も昔も変わらなくて面白いなと思いました😂
地域によってはおでんの味付けや具材も違いますが、始まりは「豆腐田楽」だったんですね🙏
何百年後かには、今の私たちが知ってるおでんも、姿形が違う別の何かに変わっていたりするかもしれませんね。。😉笑
プライバシーポリシー|サイトマップCopyright © Dojima Medical International All rights reserved.