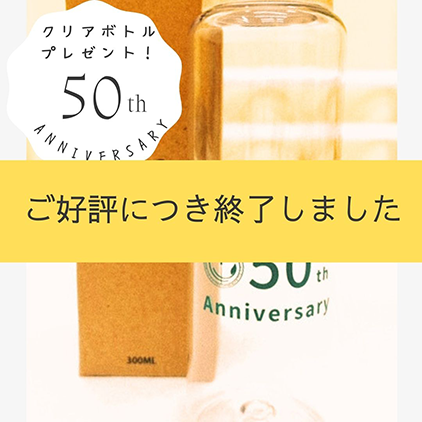スタッフブログ
ちまき😃
カテゴリ:スタッフからお知らせ
皆様こんにちは!
鍼灸あんま師の中別府です🙇
先日患者様に端午の節句ということで「ちまき」と「柏餅」頂きました😌🎶

関西のちまきと九州南部でのちまきは見た目も味も全く違いびっくりしました😆
鹿児島のちまきはこんな感じです↓↓↓

関西のちまきは白いのに対し、鹿児島のちまきは茶色なんです!これが私の小さい頃から慣れ親しんでるちまきです笑😆
このちまきにきな粉をつけて食べるのが美味しいです♡
九州南部では「ちまき」=「あくまき」っていいます😊
【ちょっとした雑学としてインターネットから引用させて頂きました、、😌🙏】
「あくまき」は、主に端午の節句で食べられる鹿児島県独特の餅菓子で、“ちまき”と呼ぶこともある。関ヶ原の戦いの際、薩摩の島津義弘が日持ちのする食糧として持参したのがはじまりだという説がある。保存性が高いことと、その腹持ちの良さから、薩摩にとって長く戦陣食として活用され、かの西郷隆盛も西南戦争で食べていたといわれる。こうした背景から、男子が強くたくましく育つようにという願いを込めて、端午の節句に食べられるようになったといわれている。
「あくまき」は、もち米を木や竹を燃やした灰からとった灰汁(あく)に浸した後、そのもち米を孟宗竹(もうそうちく)の皮で包んで、灰汁水で数時間煮込んでつくられる。灰汁に含まれるアルカリ性物質がもち米の繊維を柔らかくするとともに、雑菌の繁殖を抑え、長期保存ができるようになる。高温多湿で食糧が腐敗しやすい鹿児島県において、まさに先人の知恵がつまった料理である。
ここまで読んで下さりありがとうございます😌🙏
プライバシーポリシー|サイトマップCopyright © Dojima Medical International All rights reserved.